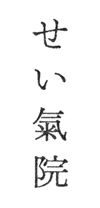野口整体
日本には「整体」という言葉は一般化していますが、こちらのページではその整体の原点に当たる野口整体について、その概要を簡単に記すことにします。
整体の原点
「野口整体」という呼び名は、整体法の創始者である野口晴哉(1911~1976)の名に由来します。この野口によって昭和20年頃よりまとめられた「人間が全力を発揮して生きるための教育(体育)」が現代の整体の原型となっています。
これが現在いろいろな場面で使用されている「整体」という言葉とは性質があまりに異なるため、それらと区別するように(主に外部から)「野口整体」と呼ばれるようになり、今日にいたります。
なお野口が設立した公式の後継団体は世田谷にある公益社団法人 整体協会に限られます。それ以外で「野口整体」を標榜している団体もしくは個人は当院も含めて傍系、ないし亜流にあたります。
教義面では、もともと体の中にある潜在体力(気力)をより所とする「自立した健康生活」の確立を目的としています。人間の潜在体力を発揮させるために「気の交流と活性化」を積極的に行う方法を考案し、奨励しました。その代表とも呼べるものが「愉気」と「活元(相互)運動」です。
また野口は整体を生きるための教養と称して、その理念を伝えるべく、講義や講習会等を精力的に開きした。野口が行う講義の在り方は意識に言い聞かせる説得的話法ではなく、意識を透過して潜在意識に語りかけ、当人が無意識のうちに丈夫になる方へ動いていくための技術として「潜在意識教育」を提唱し、実践しました。
これらの手法は成人の健康指導に当てるばかりでなく、生まれる前の赤ん坊(胎教)や、幼児・母子関係に対する教育(心理指導)にも適用されています。記憶の蔵とも呼ばれる潜在意識の内からその人の生命活動を萎縮せしめる一切の観念を消失させ、無垢なる心で生活することを良しと考え、こうした心の状態を「天心」と呼んでその啓発にも努めたのです。
創始者の没後およそ半世紀が経とうとする今日、その死生観や病気に対する見方、妊娠・出産・育児のに関する智恵に幅広く有用性が認められはじめ、徐々に注目が集まっています。
野口整体という整体は存在しない?
実は創始者 野口晴哉による「野口整体」という発言の記録を文献から見つけることはできません。ですから厳密にいうと野口整体は俗称であって「定義」を確立することはできないのです。
ただ現実には「野口整体」という呼び名で、その技法や考え方が取り扱われていることも多く、やはりそこには一つのまとまりを持った思想や技術の体系があります。
野口整体には教育や医術、そして一つの宗教観にも繋がる死生観など、人がよく生きるため教養が込められています。
現在では直系・傍系を含めた複数の弟子や異分野の研究者によって、自由かつ発展的、個性的に継承されていいます。
以上のような理由から「野口整体」に興味をもたれた方は必ず、野口晴哉の著作に直に触れられるように当院ではつよくお勧めします。
現在ちくま文庫から『整体入門』『風邪の効用』『体癖』、また整体協会全生社からは『整体法の基礎』をはじめ、多数出版されています。どの書籍にも整体の根本思想に通底する具体的事例が活き活きと綴られています。
一冊の本との出会いが人生を変えることがあります。野口晴哉の著作に触れることは、自分の「いのちの力」に気づくきっかけになると思います。
<野口整体の用語>
愉気法(ゆきほう)
体の緊張をゆるめ心をやすらかにするための気の手当てです。通常二人一組となって、どちらが一方がもう一人に手を当てて行うのが基本の型となります。ただし手を当てることは形であって本質ではありません。愉気の根本は、深い愛情を前提とした関心をもって、無心に見守る心が相手の潜在体力を煥発する力となります。
ちなみに、愉気法が通常二人以上で行うのに対し、自分の身体のどこかに意識を集め、気を活性化する方法を「行気法(ぎょうきほう)」と言います。
活元運動(かつげんうんどう)
無意識のうちに身体のバランスを取っている自律神経や錐体外路系の機能を活性化するための運動です。
なお活元「運動」と名前が付いていますが「このように動く」という決まった動作の形はありません。正しい準備動作、もしくは愉気による正しい気の誘導によって「今のその人に最適な運動」と発現します。
意識を沈めて無意識を開いて行うため、感情のはたらきを快活にし敏感な身心を育みます。ちなみに仏教の坐禅が止まって行うのに対して活元運動は「動く禅である」と評されることがあります。
整体操法(せいたいそうほう)
整体操法とは野口整体で扱う身体を刺戟する技法のことです。
元々は戦時中に当時の日本にいた民間療法家が一堂に会して、それぞれの技術を出し合ったものを一つ一つ検証し、効果のあったものだけを野口の主動によってまとめた手技療法(手で行なう治療技術)の総称でした。
当時の手技療法家の多くは、身体を物理的なもの(機械のような構造)とは考えておらず、生体エネルギーとしての「気」の概念を生命活動の根本として捉え、そのエネルギーの浄化、あるいは活性化を目的とするものが大半を締めていました。
全般に「自然生命の秩序に対する信頼」を基盤とした技術であり、技術は「生命に対する礼の心」を具現化した「型」によって行なわれます。
体癖(たいへき)
体癖とはその人の生来の感受性が固有の動作の習性を生み出し、体型をも作っていくという人間の見方です。
野口は十代のころから一日あたり百数十人の身体を観るという生活を生涯続けました。その中で人間に内在する見えない「波」のはたらきに気づきます(いわゆるバイオリズムのようなもの)。この波の性質によって生じてくる個性を分類した結果「いつも同じような疲労の仕方をする人」や「似たような行動(生活)をする人」のモデルが浮かび上がってきました。
仮に同じ言葉をかけ、同じ刺激をしても受け取り手の感受性によってその反応や結果は異なります。このような問題に対し、体癖の分類化によって整体指導の精度や再現性、客観性をある程度まで高めることに成功しました。
野口が人間に触れる際には必ずその人「個人」ということから出発し、最後まで個人の理解に注力することによって、人間を理解するうえで有益な座標軸を確立したと言えます。
全生思想(ぜんせいしそう)
整体は潜在体力としての気を活性化することで、今を十全に生き切ることをもって健康生活の基礎としています。
身心が整っていると自然と良い空想(意欲・要求)が沸き、その実現のために活発に働き、心地よく疲れ、深く眠りまた活力を養うことができると考えるのです。
全身の張弛のバランスを整えることで、はつらつとした身心を主体的に保つことを整体指導の目的としています。
潜在意識教育(せんざいいしききょういく)
人の心の構造は、受胎した時から発育の過程で入り込んだ観念や思い込みが無意識のうちに自身と一体化し、絶えず現在意識に作用します。
よって今の行動を自分で選びとっているつもりでも、実際は認識できない心の中の漠とした「何か」に動かされて人は行動をしています。
潜在意識教育の目的は、このように形成された無意識の観念のうち、生命の自在性を失わせているものをつき止め、そのような観念の払拭、もしくは方向転換を図り生命本来の力を十全に発揮させることです。
潜在観念を無ならしめ、意識が形成される以前の心(天心)が身体上に顕現することで、例えば自分が病弱であるとか、臆病であるといった思い込みから解放され活き活き生きるようになることが目的です。
こうした「人間を行動させていく力は意識ではなく、むしろ潜在意識や無意識にある」という着想は、もともとは心理学の催眠や暗示という分野で発見されたものですが、野口晴哉によって心理指導の中に体の生理的性質や働きをも組み込まれた独自の形になりました。これが整体式の潜在意識教育です。