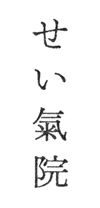体癖各論 捻れ型(七種・八種)
動作の基柱
腰椎3番:泌尿器型
体型
捻れ型は若い時は痩せているが、中年以降になると側副が発達して樽状の体型になる。同じ捻じれ型でも七種が骨太、筋肉質であることが多いのに対し、八種は特に胴が太い。
八種は顔は四角くエラが張っていて噛む力が強い(顎関節症などは捻れ型の人がなりやすい)。疲れると頬骨が出っ張ったり、顔があつぼったく腫れてきたりする(むくみやすい)。
捻じれ方は下腿が太く立派である。相撲や柔道、レスリングに向いた体系である。
体質(骨太・筋)
八種は泌尿器がくたびれやすく。偏り疲労を起こすとまず小便の出に影響する。男性の場合尿が割れて飛び散ったり、勢いがなくなる。またむくんで朝なかなか起きられなくなったり、身体が重たくなったりしやすい(梅雨時、夏場など湿気に弱い)。例えば八種がくたびれて整体を受けると、トイレに何度も行くなど。
疲れた場合は顔が腫れぼったくなったり、茶色くなったりするが、疲労がぬけるとまた白く戻る(全般に肌は黒っぽい人が多い)。疲労が皮膚に影響することも多く、急に体が痒くなるような湿疹や、帯状疱疹などはみんな捻れ型(八種)の人がよくなる病気である。
七種・八種ともに筆圧の強い人が多い。筆を持たせるとぐねぐねと癖の強い字を書く。そして大抵曲がる。
七種が禿げる時はおでこの真ん中から生え際が上がっていく。八種は毛が薄くなっていく。
七種は緊張したり、力を入れたりする場面になると無意識に奥歯を嚙んでいる。八種は顎関節症になりやすい。
歳を取って股関節の手術をする人は捻じれ方が多い。また若くして脳溢血で亡くなるような人は七種を含んでいることが多い。
捻じれ方の汗のかき方は上半身が右なら下半身は左というように互い違いになる。さらに鼻や額や脇の下に汗の多いのは八種の特徴である。
八種の子供の要求を抑えると、中耳炎や膀胱炎になりやすい。
性格・感受性(勝ち負け・質より量)
捻じれ型は「勝ち負け」に敏感である。七種は勝負事を好むのに対し、八種はむしろ嫌いな人が多い(負けるのが嫌)。
捻れ型は若いうちはすぐにケンカをする。ケンカをしてエネルギーの鬱散がついてからなら落ち着いて話ができる。往来で揉み合っていたり車の運転席からどやしつけたりしている男を見ると(見なくてもわかるが)たいてい七種である。八種は勝てそうな相手を慎重に選んで高圧的に振舞ったり可愛がったりする。
七種が「勝とう」とか「やっつけてやろう」と思うのに対して、八種はひたすら「負けないですむ」方法を考える。
八種は負け戦を買って出て、じっと耐えつづけることに美学を感じる。「負けて当然」という状況だと気にせず頑張れるからそうするのであるが、七種ならこのようなことは絶対にしない。
八種の子供は兄弟や友達など具体的な対象と比較されると途端に意欲をなくしてしまうことがある。「お兄ちゃんのほうが○○だ」、とか「お隣の○○君はもっと□□だ」などは禁句である。八種の子供には歴史上の偉人などを紹介すると、密かに張り合おうとする。
八種は大言壮語を吐いてその言葉に酔う(不安を誤魔化している)。またエネルギーが余ってくると話を盛りはじめる。自分でも気づかないうちに針小棒大になって「すごく○○だった」などと言っているが、実際に確認するとそれほどでもないことはよくある。
七種はボリューム感というものに惹かれやすく、他人の喧嘩でも選挙演説でも声が大きいと言っていることまで正しいと思い込む。音楽でも内容よりも音量に引っかかる。
人付き合い
何でも「上⇔下」で評価して見るので、グループの中に捻じれの人が一人交じるとザワザワしてくる。ザワザワしてるところに九種が入ると「しん…」とする(人間ドライアイス)。三種が入るとほっこりと温かになる。五種なら「カチ、コチ…」と時計の音でも聞こえそうなほどテキパキしてくる。五種の場合は無駄話をしてても何か目的やゴールを感じさせるような内容になっていく。
八種は情にもろく、義理を重んじる。上下関係の中では上に従順、下には高圧的になりやすいが、そのぶんよく面倒もみる。リーダーシップ的に大勢を一度に見るというよりも、一対一形式で「あなたはこうした方がいい」などと言ってお節介を焼く。必ずしも喜ばれるかというとそうでもないが、相手のために情熱的になれる体癖である。運動部の顧問や監督などにも八種は多い。
七種は贈り物というと、大きなものを送った方が良いと考える(質より量)。
生き方(職業)
歴史上の立志伝中の人物はたいてい七種である。九種の人生も苦労の連続だったりするが、九種はそういう苦労したことを他人に見せまいとする。七種はどれだけ苦労してそれを成し遂げたかを人にも言うため、記録に残っているのは七種が多い。
七種にとっては仕事もすべて戦いになる。経営者や事業主なら他所から抜きんでようとする。勤め人なら同僚の中で一番になろうと考える。そういう過剰に勝とうとする心が潜在意識下の劣等感と結びつくと絶えず人の目につくように行動し、仕事は自分の力を他にアピールするための示威行為となる。当然スポーツや武道の競技者にも七種は多い。軍人や消防士などにも向いている。
八種はこつこつと努力を積み重ねて、生涯苦行の途上に生きるような生活をする人がいる。またそうやって苦しいことに耐えていることで不安をごまかし、安心する。七種のように白黒はっきりした世界で戦い続けるよりも、職人や宗教家など自分だけの世界で求道的に生きる方がしっくりいく。八種は自分で自分を求道者だと思っているが、九種は他人から求道的と評されることはあっても、自分では「これが当たり前、普通に生きている」と思っている。
社会的立場としては七種は常にトップをねらうのに対して、八種は自分が長になるとグラグラして途端に不安定になる。人格、実力的に「この人はすごい」という人を認めて、腹心という立場に収まると手腕を発揮しやすい。
疲労傾向と対策
八種は負けを無理やり認めさせられたり、頑張りようがない状況に陥ると泌尿器系の働きが悪くなり、小便が閊える(気がついたら膀胱がパンパン、など)。子どもならオネショで親に反抗する(無意識なので親はムキになって対立しないこと)。身体の水回りが悪くなりやすいので梅雨時の湿気にも弱い。そこからさらに側腹が張って厚ぼったくなると頑固になる(ぎっくり腰予備軍)。
八種の子どもは風邪を引く前に暴れる。発症する頃には扁桃腺が腫れて熱を出す。偏り疲労が一定に達したら、減食をすると少し調子が良くなる(八種の現職は苦行的達成感にもつながる)。動作で修正するなら、仰向けになって身体を横倒しにして側副を伸ばすとよい。また横になってごろごろ転がりながら足と手を反対にして雑巾のように脇腹を捻じるのも効果的である。
何より、エネルギーが鬱滞してきたら密かに張り合えるもの(対象)を見つけて、せっせと頑張れる状況を作ることを考えるとよい。
捻れ型が濃く表れている人物(敬称略)
- 七種
- 岩崎弥太郎、中西太、大山倍達、マイク・タイソン、高嶋ちさ子、吉田秀彦、室伏広治(七種と一種)
- 八種
- 浅沼稲次郎、江夏豊、小沢一郎